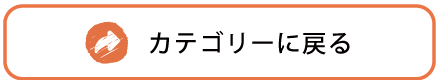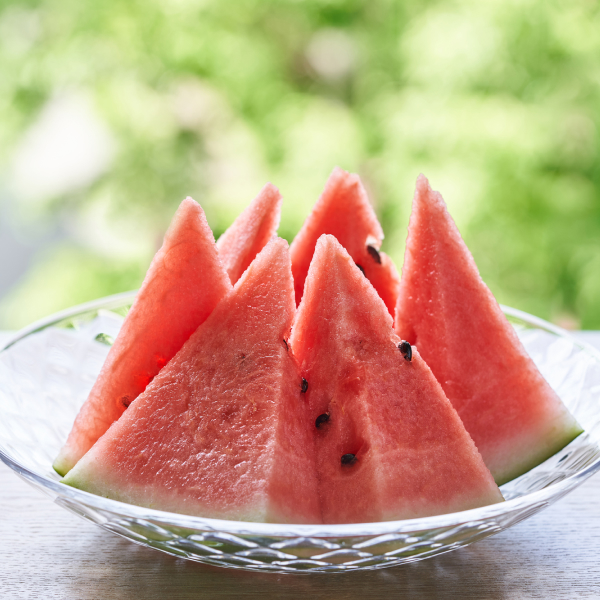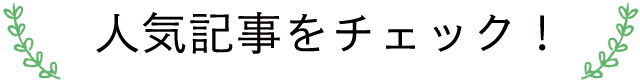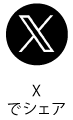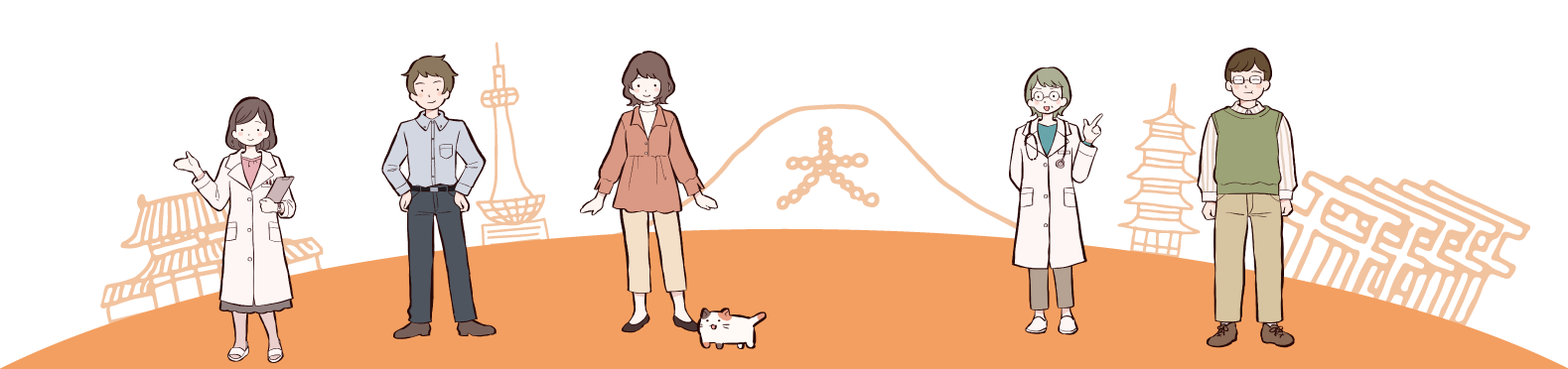ムクナ豆はインド原産のマメ科植物です。日本ではハッショウマメとも呼ばれ、江戸時代に各地で栽培されていました。種子にはL-DOPAが豊富に含まれ、パーキンソン病の補助治療にも用いられます。ただし、L-DOPAの過剰摂取は副作用を引き起こすため、調理による除去が必要です。世界各国でさまざまな調理法があり、日本では煮たり茹でたりして食べます。ムクナ豆には免疫力向上、骨や歯の強化、腸内環境の改善などの健康効果もあります。特にタンパク質やカルシウム、食物繊維が含まれていて、適切な摂取により健康維持に役立ちます。
ムクナ豆とは?
ムクナ豆は、インド原産の多収穫なマメ科植物です。日本ではハッショウマメと呼ばれ、江戸時代には各地で栽培されていました。ムクナ豆の特徴の一つとして、L-DOPAを豊富に含む点が挙げられます。特に種子には非常に多く含まれています。L-DOPA(ドーパ)は哺乳動物において、神経伝達物質であるドーパミンやアドレナリンの前駆体として重要であるため、ムクナ豆はパーキンソン病の補助治療として用いられることもあります。さらに、ムクナ豆は一般的な豆と同様に、たんぱく質、でんぷん、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどを豊富に含みます。
しかし、L-DOPAを一度に過剰摂取すると、心拍数の増加、嘔吐、下痢、食欲不振などを引き起こすことがあります。そのため、ムクナ豆を食品として利用する場合は、L-DOPAを除去する必要があります。
L-DOPAは水溶性であり、調理によってムクナ豆から除去することが可能です。そのため、ムクナ豆は世界各国でさまざまな調理法によって食用とされています。例えば、インドネシアではムクナ豆の種子を水に漬けて種皮を取り除き、煮る、あるいは発酵させて食べます。インドでは若い莢や種子を食用とし、マレーシアでは種子を繰り返し茹でた後、種皮を除いて食べます。アフリカ東部では十分に水につけた後、何度も水を換えながら煮て食べ、ナイジェリア東部では粉にして食べることもあります。日本では、主に煮たり茹でたりして、飴やきんとんにして食べます。
ムクナ豆の効果
■免疫力を高める効果
ムクナ豆に含まれるタンパク質は、体を構成する細胞になるほか、体を細菌やウイルスなどから守る免疫細胞のもとにもなります。免疫細胞が活性化されると、免疫力を高めることにつながります。
■丈夫な骨や歯をつくる効果
ムクナ豆に含まれるカルシウムは、強い骨や歯をつくり、体を支える重要な働きがあります。
カルシウムとともにマグネシウムやリンも骨をつくる成分になります。カルシウムが2~3に対して、マグネシウムは1のバランスが良いとされています。リンも骨をつくる成分ですが、一緒に摂るとカルシウムの吸収を妨げます。リンは肉類や魚介類など多くの食品に含まれ、過剰摂取となりやすいため、カルシウムの摂取量を増やすことが重要です。
また、吸収したカルシウムを効率良く骨に利用させるためには、適度な運動を行い、骨に負荷を与えることも重要です。
■腸内環境を整える効果
ムクナ豆に含まれる食物繊維は、腸内に溜まった不要な老廃物や有害物質を吸着し、体外へ排出する働きがあります。また、腸内の善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やす働きもあるため、腸内細菌のバランスが良くなり、腸内環境の改善に役立ちます。
腸内環境が整うことで、便秘の予防や改善にも効果が期待できます。

こんな方におすすめ
●免疫力を高めたい人
●骨や歯を強くしたい人
●便秘で悩んでいる人

おさらい
●ムクナ豆はインド原産のマメ科植物で、日本ではハッショウマメと呼ばれ、江戸時代に各地で栽培されていた
●パーキンソン病の補助治療にも用いられるL-DOPAを含むが、副作用を引き起こすため、調理による除去が必要
●ムクナ豆に含まれる栄養素は、免疫力向上、骨や歯の強化、腸内環境の改善が期待できる

・ムクナ豆の歴史と色の特徴(日本家政学会誌 2020年 71巻 5号 p.280-288)
・調理によるムクナ属マメの一般成分およびL-DOPAの変化(日本調理科学会誌 2012年 45巻 6号 p.438-446)
・ムクナ豆味噌の調製および調製過程における抗酸化活性の変化(日本調理科学会誌 2017年 50巻 5 号 p.174-181)
・完全図解版 食べ物栄養事典(発行所 株式会社主婦の友社)