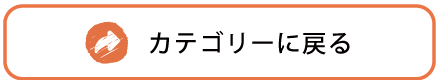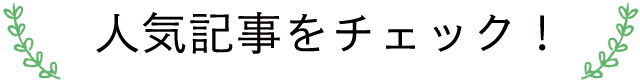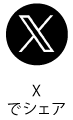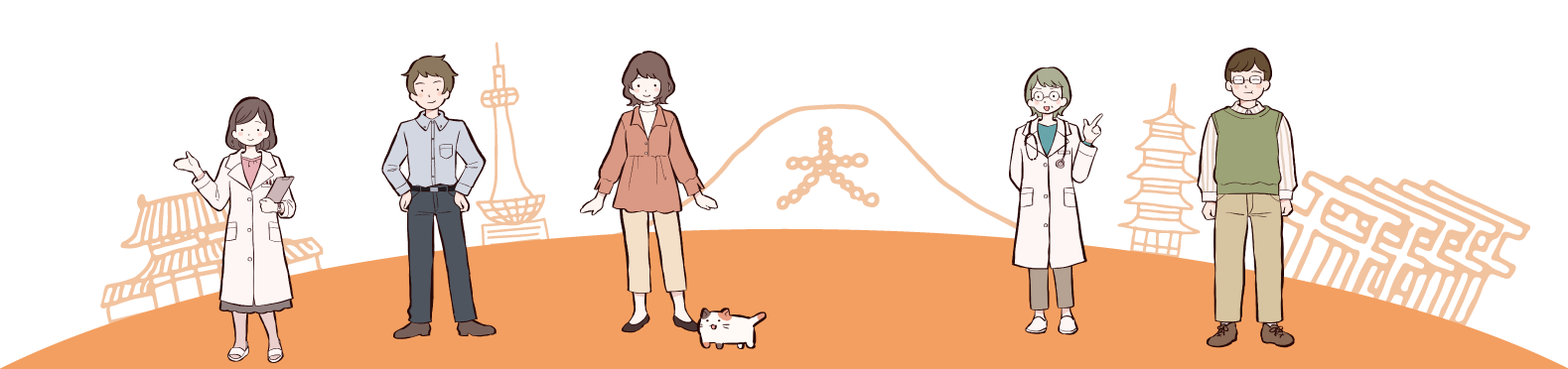かんぴょうは、ウリ科のユウガオを細長く削り乾燥させた食品で、中国から伝来し古くから日本で栽培されています。ユウガオは3種類に分類され、かんぴょうの材料となる、丸・だるま型が主に利用されます。製造工程では帯状に削り天日干しし、精進料理や寿司に使われます。栄養面では食物繊維が豊富で腸内環境を整え、便秘改善に役立ちます。また、カルシウムを含み骨や歯を強くし、カリウムによる高血圧予防効果も期待ができます。
かんぴょうとは?
かんぴょうは、ウリ科に属するユウガオの果実を細長くむき、乾燥させたものです。原産地は北アフリカまたはインドとされ、日本には中国から伝来したと考えられています。『源氏物語』にも記載があることから、栽培は非常に古くから行われていたことがわかります。
ユウガオが属する瓢類は、大きく3つの型に分類されます。
1つ目は、果肉をくり抜いて容器として利用されるヒョウタン型(食用にはなりません)。
2つ目は、苦味があり食用には適さないものの、主に台木として使われる細長型。
3つ目が、かんぴょうの材料となる、丸・だるま型です。この丸・だるま型の品種は、ほとんど分化が進んでおらず、栃木県農業試験場で育成された「しもつけしろ」と「しもつけあお」が主流です。これらは、かんぴょう専用の品種とされています。
かんぴょうの製造では、皮を剥いた果肉を幅3.3cm、厚さ2〜3mmほどの帯状に薄く削り、長さ約2.5mの状態にします。それを竿にかけ、天日で乾燥させます。かんぴょうは主に精進料理や寿司、冠婚葬祭の料理に利用されますが、東北や北陸地方では、苦味のない細長型のユウガオが煮つけ、あんかけ、汁の実、漬物の材料としても食べられています。
かんぴょうは食物繊維を非常に多く含み、ゴボウと比較してもその量はかなり多いです。それにもかかわらず、柔らかくなめらかな食感を持っています。また、栄養素としてカルシウムやカリウムなども含まれており、栄養価の高い食品です。
かんぴょうの効果
■腸内環境を整える効果
かんぴょうに含まれる食物繊維は、腸内に溜まった不要な老廃物や有害物質を吸着し、体外へ排出する働きがあります。また、腸内の善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やす働きもあるため、腸内細菌のバランスが良くなり、腸内環境の改善に役立ちます。
腸内環境が整うことで、便秘の予防や改善にも効果が期待できます。
■丈夫な骨や歯をつくる効果
かんぴょうに含まれるカルシウムは、強い骨や歯をつくり、体を支える重要な働きがあります。
カルシウムとともにマグネシウムやリンも骨をつくる成分になります。カルシウムが2~3に対して、マグネシウムは1のバランスが良いとされています。リンも骨をつくる成分ですが、一緒に摂るとカルシウムの吸収を妨げます。リンは肉類や魚介類など多くの食品に含まれ、過剰摂取となりやすいため、カルシウムの摂取量を増やすことが重要です。
また、吸収したカルシウムを効率良く骨に利用させるためには、適度な運動を行い、骨に負荷を与えることも重要です。
■高血圧を予防する効果
ナトリウムは体にとって必要なミネラルですが、摂り過ぎると高血圧の原因になります。
かんぴょうに含まれるカリウムは、過剰なナトリウムを尿として排出する働きを促すため、高血圧の予防に効果があります。

こんな方におすすめ
●便秘で悩んでいる人
●骨や歯を強くしたい人
●高血圧が気になる人

おさらい
●かんぴょうは、ウリ科のユウガオを細長く削り乾燥させた食品
●ユウガオは3種類に分類され、かんぴょうの材料となる、丸・だるま型が主に利用される
●食物繊維が豊富で便秘改善、カルシウムを含み骨や歯を強くし、カリウムによる高血圧予防効果も期待できる

・完全図解版 食べ物栄養事典(発行所 株式会社主婦の友社)
・実用版・オールカラー 食品図鑑(発行所 女子栄養大学出版部)
・地理的表示(GI)登録で知名度向上(近畿農政局) https://x.gd/1CuJZ